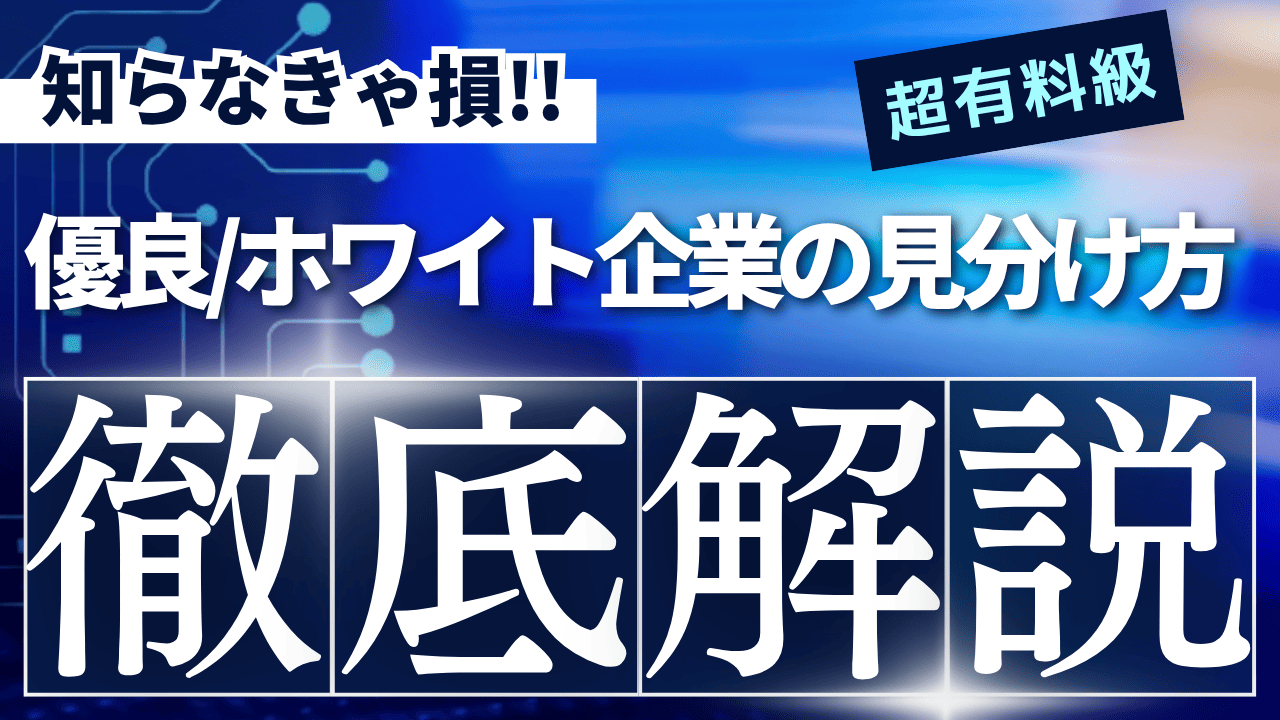求人票やホームページを見るだけでは、目の前の企業が本当に「優良企業/ホワイト企業」なのか、なかなか判断できないものです。
今回は、そんな悩みを抱える方のために、優良企業/ホワイト企業の見極め方を具体的かつわかりやすく解説します。転職で後悔しないための知識を、ここでしっかり身につけましょう。
結論:自身の転職の軸を把握した上で、以下の5つの観点から見つけた or 紹介された企業を評価し、納得できる企業を選ぶことが大事です。
本記事では、上記のそれぞれの5つの観点について、詳細に説明していきます!
- やりたいことが出来るのか
- 年収
- 個人の成長性
- 働きやすさ
- 安定性
5つの観点のそれぞれの確認項目はこちらになります!
| 評価ポイント | 確認項目 |
|---|---|
| やりたいことが出来るか | ・企業の事業内容 ・業務内容 |
| 年収 | ・業界平均/ライバル企業との比較 ・将来の年収推移 |
| 個人の成長性 | ・成長しやすい環境であるか ・転職の市場価値が上がるか |
| 働きやすさ |
・残業 ・人間関係 ・有給について ・休日数 ・企業の雰囲気 ・平均勤続年数 ・福利厚生 ・勤務地 |
| 安定性 | ・会社の継続性 |
やりたいことが出来るか
やりたいことが出来るかの調査を実施する際に確認するべき項目は「会社の事業内容」と「職種ごとの仕事内容」になります。
※注意点としては、どんなに調査を行って理解したとしても、調査した結果の仕事のイメージと実際の業務内容にはギャップがある可能性はあります。「百聞は一見にしかず、百見は一験にしかず」と言えるでしょう。
事業内容の確認方法
事業内容を知るには、まずは会社の公式ホームページを確認するのが基本です。多くの方も、ここを出発点に情報収集を進めているかと思いますが、加えて以下のような情報源にも目を通すことで、理解がより深まります。
- IR資料/投資家向け資料
- 新卒、中途採用ページ
- 特定の製品に関するネット記事
IR資料/投資家向け資料
現在の会社の強みや、今後注力していく分野を把握することができます。
自分が関わりたい領域が会社の強みであるか、または今後力を入れていく分野であるかを知ることで、やりたいことに近づく一歩となります。
内容が難しいと敬遠されがちですが、実は分かりやすくさまざまな情報がまとめられているため、一度目を通してみることをおすすめします。
新卒、中途採用ページ
企業の全体像をつかむには、まず採用ページの確認がおすすめです。社員の一日の流れなどが載っていることもあり、働くイメージがしやすくなります。
ただし、採用ページは魅力を強調して作られているため、実際とのギャップがあることも。鵜呑みにせず、参考程度にとどめましょう。
特定の製品に関するネット記事
色々確認する中で特定の製品名などが出てきますが、製品名をそのままネット検索することでより分かりやすいネット記事が見つかります。
もし紹介したサイトだけではイメージがつかみにくい場合は、気になるキーワードで個別に検索してみると、役立つ情報が多く出てきます。
職種ごとの仕事内容の確認方法
仕事内容に関してはデスクトップリサーチでは少し難しい部分があります。理由としては前述の通り、実際の業務を通して分かることが多いためです。
と言いつつもそのイメージを近づける方法が3つありますので、それをここで紹介します。
- 未経験の職種への転職の際にはjob tagを使って、おおまかなイメージを掴む
- 面接で不明点を聞き、仕事内容の認識を合わせる。
- OB訪問や友人を通して確認する。
厚生労働省の「job tag」(未経験の職種に転職する際は一読必須)
各業界の職種のおおまかな業務内容や必要なスキルに関しては厚生労働省の「job tag」を確認することで理解できます。
例えば、システムエンジニア(受託開発)の仕事内容などがざっくり記載されています。
job tagで仕事内容を確認したい場合はこちら!
面接で不明点を確認する
求人情報だけでは実際の仕事内容をイメージしづらいこともあるため、ある程度自分なりに仮説を立てたうえで、面接時の逆質問などで確認すると良いでしょう。
自身のやりたいこを伝えて確認することは両者の認識の齟齬を無くす上で重要なので、気になる点は積極的に質問しましょう。
OB訪問(身近に行きたい会社/職種で働いている人を見つけ、話を聞く)
可能であれば、実際にその企業や職種で働く人の話を聞くのが理想です。身近にいない場合は、「Matcher」などのOB訪問アプリや、友人のつながりをたどるのも有効です。
ただし、聞けたとしてもそれはあくまで一人の意見。感じ方に個人差があるため、できれば複数人から話を聞けると、より客観的な判断ができます。
年収の確認ポイント
年収に関しても単に求人の年収を見るだけでなく、以下の観点も確認することでより将来がイメージしやすくなります。将来を見据えた転職のためにも一緒に確認しましょう。
- 平均年収との比較(職種/業界平均年収、ライバル企業の平均年収)
- 転職先の年収の伸び率
平均年収との比較
平均年収の比較の分析は以下の3点が重要になります。
- ・職種/業界は本当にそこで問題ないか
- ・業界内では企業の年収はどれくらいの立ち位置か
- ・ライバル企業との比較
職種/業界は本当にそこで問題ないか
これは、実は最も重要なポイントの一つです。というのも、業界によって年収の相場が大きく決まってしまうからです。
たとえば、魚(年収が高い求人)がたくさんいる池(職種/業界)と、ほとんどいない池(職種/業界)があったら、どちらで釣りをするかは明らかですよね。もちろん、魚(年収が高い求人)が多い池(職種/業界)を選ぶはずです。
それと同じように、働く業界を選ぶときも、「どこで勝負するか」を正しく見極めることがとても大切なんです。
例えば、IT業界(エンジニア)と卸売業界(スーパーの店員)の年齢別の平均年収のマックスを比較してみましょう。
| 職種 | 年齢別平均年収のマックス年収 |
|---|---|
| エンジニア | 737万円(45-49歳) |
| スーパーの店員 | 412万円(45-49歳) |
参考元(job tag)
スーパ店員
システムエンジニア(受託開発)
業界や職種によって、年収の上限はある程度決まっています。本当にその業界で良いのか、一度立ち止まって考えることも大切です。最近は未経験からでも異業種への転職がしやすくなっており、年収の高い業界へチャレンジすることも十分可能です。もし異業種への転職を検討している方は、ぜひSmaDeciにご相談ください!
※スーパ店員という職業を否定するわけではありません。年収という観点では評価した場合はエンジニアなどの職種の方が良いということです。
同一職種/業界内での年収比較
次に業種/業界内での比較になります。こちらは検討している企業の年収が業界の中でどれくらい高い or 低いのかを理解することが大事です。
業界内の年収推移は先ほど紹介したjob tagを活用することで確認できます。
年収が平均より低い場合は、なぜそうなのか、そして年収以外に本当にメリットがあるのかを冷静に見極める必要があります。
ライバル企業との比較
こちらは多くの方がされていると思いますが、他のレベル感が近い企業と年収を比較することも大事です。実際に企業の年収を分析する際に参考になるサイトを紹介します。
1つはOpenWorkです。各企業の口コミをまとめたサイトになります。データ数も多く信頼度は高いです。OpenWorkでは企業同士で諸々比較しやすくなっているため、調べるには適しています。
2つ目は転職会議です。OpenWorkに十分なデータがあればそれだけで問題ありませんが、情報が少ない場合は複数の口コミサイトを活用して年収を確認するのがおすすめです。その際に、転職会議もあわせて使うと良いでしょう。
転職先の年収の伸び率
転職先の年収の伸び率についても確認が必要です。転職の初めは高かったとしても、その後伸び率が悪い場合は次の転職を考える必要性が出てくるのでざっくりどれくらい将来的に貰えるのか考えておく必要性があります。
個人の成長性(市場価値が上がるかの確認)
個人の成長性は、将来の転職やキャリアの選択肢を広げるうえで重要です。
変化の激しい時代だからこそ、自分の市場価値を高め、どこでも求められる人材を目指す必要があります。
成長性(市場価値が上がるか)の確認の観点としては「転職実績」と「成長できる環境であるか」になります。
- 転職実績(キャリア事例から、どんなキャリアが選択可能になるのかを理解する)
- 成長できる環境であるか(社内制度や社員の雰囲気、仕事内容から判断する。)
転職実績の確認
転職実績の確認とは、その企業に勤めていた人が次にどんなキャリアを歩んだかを見ることです。そこで働くことで市場価値が高まるのかを知るための、有効な判断材料になります。実績の確認方法としては2つあります。
ONE CAREER PLUS
ONE CAREER PLUSでは、様々な人のキャリア選択の事例が確認でき、なぜその選択したのかや転職時に他に検討していた企業など詳しい情報が見れます。
ONE CAREER PLUSはこちら
openwork career
こちらは転職専用のSNSに近いサービスでキャリア事例に加えて、キャリアの悩みの情報交換が出来るサービスになっています。
openwork careerはこちら
※全体的にまだ事例が少なく、特にベンチャーや中小企業の情報は少ない傾向があります。どこまで教えてもらえるかは分からないですが、転職エージェントに相談するのも一つの手です。
成長できる環境かの見極め
成長できる環境かの見極めに関しては①会社側が社員の育成をサポートする制度があるのか、②社風や社員の雰囲気はどうか、③仕事の内容自体が市場価値が上がりそうな仕事か、の3点があります。
会社側が社員の育成をサポートする制度があるのか
会社の採用ページやホームページを確認し、育成に力を入れているのかを確認します。具体的な制度としては以下が充実していると良いです。
- ・研修制度が充実している(特に未経験からの転職では重要)
- ・資格取得の補助制度がある
- ・メンター制度が整備されている
- ・そのほか、人材育成に力を入れている制度が多いほど望ましい
※注意点としては、制度を活かすには、自ら積極的に動くことが大切です。上手に活用して、自身のキャリアアップにつなげましょう。
社風や社員の雰囲気
制度に加えて、社風や社員の雰囲気も非常に大切です。社員の熱量が高くてお互いが教え合う文化があるのか、優秀な人が多いのかなども重要なポイントになります。
こちらに関してはOpenWorkや転職会議でのリアルな口コミ情報を参考に確認します。あとは実際に働いている人に聞くなどもあります。口コミは少なくとも偏りなく見るために200件は確認したほうが良いです。
仕事の内容自体が市場価値が上がりそうな仕事か
上記の内容に重複する部分もありますが、仕事内容自体が転職の市場価値を高める経験が出来ているのかを確認するべきです。
市場価値の高い仕事を見極めるのは難しいですが、少なくとも「需要のあるスキルが身につくか」「貴重な経験が得られるか」といった観点を意識すると良いでしょう。
働きやすさの確認項目
働きやすさに関しては以下の項目をそれぞれ確認したいです。確認項目は多いですが、それぞれしっかり認識しておきたいです。
- 残業時間(多すぎないか)
- 人間関係/人の良さ
- 有給の取りやすさ
- 休日数
- 企業の文化(ネガティブな文化も含め)
- 平均勤続年数
- 福利厚生
- 勤務地に関する情報
残業時間
残業時間に関しては、全業界と業界単位での平均残業時間の2つを確認して比較するのがベストです。業界によっては残業時間が高くなりやすい業界もあるので、全業界と業界単位でも比較しながら検討することが大事です。
全業界の平均の残業時間は13.7時間(令和5年のデータ)になります。残業時間に関してはopenworkや転職会議のデータを参考にした方が良いと思われます。
企業側が公開しているパターンもありますが、みなし残業などが含まれていない可能性があるため個人的には口コミサイトの方が信頼できるかなと考えています。
人間関係/人の良さ
人間関係/人の良さに関しては実際にその人によって相性だったりがあるので難しいですが、おおよその人間関係については口コミサイト(openworkや転職会議のデータ)から概要を掴めます。
具体的には体育会気質が強い人が多いや穏やかな人が多いなどが分かりますが、注意点としては1つの口コミのデータではなく、複数の口コミで同じ内容が書かれているかを確認してください。
1つだけの情報では、信頼度は低いですが何人も同じようなことを述べている場合は信頼度が高くなります。
有給の取りやすさ
休みたい時に休みが取れることは働きやすさには必要です。これも口コミサイト(openworkや転職会議のデータ)と有給取得日数及び有給取得率の平均値と比べて問題ないかを確認します。
令和5年の調査によると、平均有給休暇日数は16.9日、そのうち取得日数は11日で、有給取得率は65.3%と過去最高を記録しています。これらの水準を下回る場合、有給の取りやすさという点ではネガティブな評価につながる可能性があります。
休日数
年間休日数に関してもどれくらいあれば良いかについては以下の表に簡単にまとめています。ちなみに平均値で見ると労働者1人平均は116.4日(令和5年のデータ)になっています。休日数に関しては求人に書かれているので、そちらから確認してみてください。
補足ですが、年間休日数とは会社や事業所が定める1年間の休日数の合計を指します。なので、有給休暇やバースデー休暇、結婚休暇など取得できる日数やタイミングが異なる休暇は年間休日数に内包されません。
参考元
令和6年就労条件総合調査の概況(厚生労働省)
年間休日の平均や内訳は? 125日・120日・110日・105日って実際はどのくらい休める?(ジョブメドレー)
| 年間休日数 | 概要 |
|---|---|
| 105日 | 労働基準法での最低ラインです。これを下回ると違法のラインになります。 |
| 115日 | 平均値に近い数字。最低限欲しいラインと言えます。有給の付与数が多い場合は平均より低くても問題いです。 |
| 120日以上 | 120日は週2日の休みと祝日が休日として定められている場合がほとんどで、125日になると更に夏季休暇や年末年始休暇などが付与されている場合が多いです。 |
有給の取りやすさと合わせて確認すると良いと思います。
企業の雰囲気・文化
企業の雰囲気・文化に関しても口コミサイト(openworkや転職会議のデータ)から確認すると良いです。注意点としてはやめた方が書かれている口コミなので、若干ネガティブよりにはなりやすい可能性があります。
ただ、何人もの口コミで同様のことが書かれている場合は信ぴょう性が上がります。なるべく多くの口コミを確認するようにしましょう。
平均勤続年数
平均勤続年数が低いとブラック企業の確率が高まると言われています。一般的な企業の平均勤続年数は12-14年あたりかなと言えます。厚生労働省の令和6年の7月のデータでは、13.7年と出ています。検討している企業の平均勤続年数を知りたい場合は「会社名 平均勤続年数」のワード検索でだいたい出てきます。
参考元:令和6年毎月勤労統計調査特別調査の概況(厚生労働省)
極端に低い場合は何かしらの理由が必ずあるので、それがポジティブな理由であるか、またはネガティブな理由であるのかをしっかり見極める必要性があります。
福利厚生
福利厚生に関してもかなり評価が難しいのですが、最低限欲しい福利厚生は以下の通りです。ただ、人によってこれは絶対欲しいなどがあるので、会社に入ってから損しないためにも事前にどんな福利厚生があるのかはチェックしておきましょう。
※福利厚生には「法定福利厚生」と「法定外福利厚生」の2種類があります。一般的に「福利厚生」と言う場合は、企業が任意で提供する法定外福利厚生を指すことが多いです。今回は簡単に独自で評価表を作りました。
| あったら嬉しい福利厚生 | ・住宅関連の福利厚生 ・食費・昼食の補助 ・働き方に関する福利厚生 ・余暇やレクリエーションに関する福利厚生 |
| 最低限欲しい福利厚生(社員を大事にしている会社なら欲しい福利厚生) | ・交通費 ・健康に関する福利厚生 ・慶弔/災害関連(慶弔休暇制度やお金に関することも) ・育児/介護(該当する方は欲しいです) |
注意点としては福利厚生だけで会社を決めるのは本当に違いますので、そこだけ気を付けてください。
勤務地について
勤務地に関しては、①リモートワークがどれくらいできるのか、②勤務地は変わる可能性があるのかの2点を確認したいです。
求人や実際の面接後の質問のタイミングなどから確認すると良いです。ただ、コンサル業界などではお客さんによってはお客さんの会社に出勤しなければならないこともあるため、プロジェクトや配属によって変わりやすい環境もあります。
企業の安定性(長く勤められるかどうか)
最後に、企業の安定性についても確認しておきましょう。現在は転職しやすい状況ですが、景気が悪化した際には求人が減り、転職が難しくなる可能性があります。そうした中で、勤務先が倒産して職を失うようなリスクは、できる限り避けたいところです。
ただし、安定性の判断は非常に難しく、あくまで目安となる情報から推測するしかない点はご理解ください。社会の変化は激しいので、完全にこの企業が安全というのは絶対に断言できないです。
安定性の判断のポイントは以下の3点です。
- 斜陽産業であるか
- 決算書に問題はないか
- 社内からの将来に対する口コミに問題はないか
斜陽産業かどうか
斜陽産業とは、市場規模が縮小し、業界全体として売上を伸ばすことが難しくなっている産業のことを指します。
こうした業界では収益を上げにくいため、企業の経営が不安定になりやすく、倒産リスクも相対的に高くなります。現時点で斜陽産業とされているのは以下のような業界であり、可能であれば避けた方が無難です。
とはいえ、「その業界でどうしてもやりたいことがある」「明確な目的がある」といった場合には、業界の将来性だけで判断せず、自分の意思を大切にするのも一つの選択です。
斜陽産業の具体例
具体例は以下の通りですが、ほかにも技術革新や価値観の変化により、縮小傾向にある業界は少なくありません。
一方で、成長している市場も存在します。そうした拡大市場を狙うことで、自身のスキルや経験の価値を高め、転職市場での評価を上げることにもつながります。
- ・ブライダル業界(結婚式などを扱う業界で結婚式を行う人の減少)
- ・印刷業界(デジタル文書の普及に伴い、縮小)
- ・百貨店/デパート業界(オンラインでの買い物の普及)
決算書に問題がないか
決算書は少しハードルが高く、つい敬遠されがちですが、企業の経営状況を把握するうえで非常に重要な資料です。
本格的に読み解こうとすると専門的な知識が必要になりますが、今回は最低限チェックしておきたい4つの指標に絞って、分かりやすく解説します。
ただ、決算書も正直当てにならない可能性があります。本当にやばい企業は粉飾決算といって嘘の決算書を作ります。
粉飾決算は素人が見極めるのは無理なのですが、以下の指標は確認して損はないのでぜひ確認してみてください。確認方法は実際に自分で決算書を見て計算する方法とバフェットコードを参考にする方法があります。バフェットコードの方が見やすいので、そちらを参考にしながら計算すると良いです。
| 指標 | 概要 |
|---|---|
| 流動比率(流動資産÷流動負債×100) | 1年以内に支払い義務のある借金を問題なく支払うことが出来るかを確認するための指標です。直近で潰れないかを確認するために使います。120%を超えていると安心と言われています。 |
| 当座比率(当座資産÷流動負債×100) | こちらも直近での支払い能力を見る指標になります。流動比率と差異が激しい場合は注意です。90%を超えていると安心と言われています。 |
| 固定比率(固定資産÷自己資本×100) | 長期的な支払い能力を測る指標です。この比率は100%以下が望ましいとされています。 |
| 自己資本率(自己資本÷総資産×100) | 借金(負債)が全体の資産と比べて多くないかを確認する指標になります。50%を超えていると良好と言われていますが、業種/業界で平均は異なるので、注意してください。 |
社内からの将来に対する口コミ
口コミサイトでは、社内の社員視点からの企業の将来性についても語られています。口コミサイトは本記事で何度も出てきているopenworkや転職会議が参考になります。
これまでの内容に加えて、実際の社員や元社員による口コミもあわせて確認することで、企業の安定性をより多角的に把握することができます。
ただ注意点としては、口コミはあくまで経営に関与していない立場からの意見に過ぎません。鵜呑みにせず、他の情報と照らし合わせながら総合的に判断していくことが大切です。
まとめ
結論は以下の5つ観点から多角的に企業を分析することで、転職するべきかの判断の精度を上げることが出来ます!失敗しない転職を実現しないためにも、しっかり企業について把握しましょう。
- やりたいことが出来るか
- 年収
- 個人の成長性
- 働きやすさ
- 安定性
調べることは分かったけど、1人で全部調べるのは大変ですよね!?
SmaDeciでは上記の内容を網羅した企業分析レポートを無料作成します!
失敗しない転職を実現するためにも、SmaDeciにぜひ相談してください!